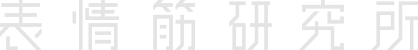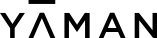columnコラム
vol.4 中村 真先生
一番つくりやすいのは幸福や驚きの表情。では、つくりにくいのは?
高齢者の方に、表情を演技してもらった調査では、笑顔はちゃんとできていたんですが、嫌悪や怒りといった他の感情は表情が弱かったり、さまざまな感情が混ざってわかりにくいという結果が出ています。つまり、はっきりしている表情が少ないんですね。
これは、例えば眉が下がったとか引き寄せられたといった顔のパーツの動きからも分析してみています。それを見ると、幸福や驚いた表情をお願いした場合は、はっきりと表情ができていましたが、他の感情の場合は表情のうえでもさまざまな動きが混ざり合って判別しにくいことがわかりました。
調査の後半では、高齢者が演技した表情を大学生に見せて、「この表情はどう見えますか」と聞いているんですが、幸福の表情は幸福と判断されるんですね。驚きもそうです。しかし悲しみや怒り、特には嫌悪感や軽蔑といった感情になると、はっきりと判別できませんでした。
ただ、この傾向は高齢者に限ったことではなく、大学生の場合でも同様なことがわかっています。私たちの普段の生活をふり返ってみても、嫌悪や軽蔑を表情にすることは避ける心理が働くので、当然といえば当然かもしれません。
また、文化の違いや環境、一人ひとりが持っている社会的な価値観によっても、よく表す表情と、あまり表さない表情があると考えられます。そして、何らかの理由で表情にすることを避けることで、表情筋の中でも普段あまり使わないものが誰にでもありそうです。
表情筋も筋肉ですから、年齢を重ねれば弱まり、表情をつくりにくくなっていきます。特に普段あまり使わない表情筋を意識的に動かし、鍛えていくことで、いつまでも自分の感情が明確に伝わる表情をつくっていくことも大切かもしれません。

―PROFILE
中村 真Nakamura Makoto
大阪大学人間科学部助手、宇都宮大学教養部講師、宇都宮大学国際学部助教授を経て、現在同教授。感情とコミュニケーションの心理学について研究。特に、顔や表情に焦点を当て、感情のコミュニケーションにおける表情と文脈の重要性、感情のあらわし方についての文化差を研究。近年は、感情と排斥行動の問題についても研究も進めている。日本感情心理学会Interna’onal Society for Research on Emo’on、日本心理学会、日本社会心理学会、日本発達心理学会、日本顔学会所属。
主な著書
「感情心理学ハンドブック」 (中村他(編) 北大路書房 2019年) 「感情心理学―感情研究の基礎とその展開」(今田・中村・古満(著) 培風館 2018年)「顔の百科事典」(分担執筆 丸善出版 2015年)「岩波講座 コミュニケーションの認知科学2 共感」(分担執筆 岩波書店 2014年)「感情心理学・入門」(分担執筆 有斐閣 2010年)「顔と心―顔の心理学入門」(吉川・益谷・中村(編) サイエンス社 1993年)「人はなぜ笑うのか―笑いの精神生理学―」(志水・角辻・中村(著) 講談社 1994年)
主な論文
「特集:社会的共生と排斥行動:問題の所在」(今田・中村(編)『エモーション・スタディーズ』4Si, 2019年)森 大毅,中村 真「音声研究における感情の位置付け(<小特集>音声は何を伝えているか) 」(日本音響学会誌 一般社団法人 日本音響学会 2015年)中村 真「大規模災害に伴う感情経験 : 東日本大震災時に経験した感情の諸側面に関する質問紙調査(1)」(宇都宮大学国際学部研究論集 宇都宮大学国際学部 2013年)中村 真「学術用語としての感情概念の検討 : 心理学における表情研究を例に」(宇都宮大学 国際学部研究論集 宇都宮大学国際学部 2012年)中村 真「社会的共生の心理学的基盤−感情のコミュニケーションと道徳的感情−」(宇都宮大学国際学部研究論集 第30号2010年)中村真,清水 奈名子,田口 卓臣,松尾 昌樹「書評 : 『グローバル世界と倫理』を読む」(宇都宮大学国際学部研究論集 宇都宮大学国際学部 2010年)
2020/11/28 更新